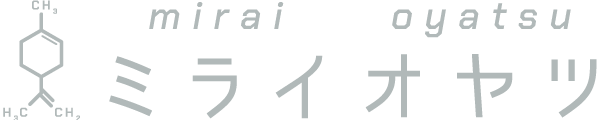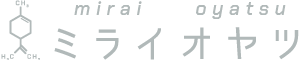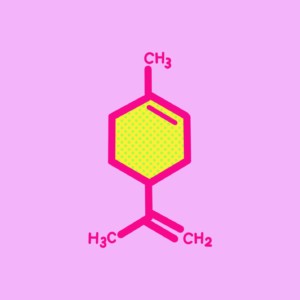香りを表現する言葉が少なすぎる件
香りのボキャブラリー
香りを表す言葉は、とても少ないです。「こうばしい」「くさい」「甘い」くらいしか、ぱっと思いつきません。では、香りを表現したいときはどうしているかというと、他のものに喩えます。
「ナッツのような香り」「バナナの香り」「張り替えたばかりの畳のような香り」「あ、ここの家、今晩カレーだな、の香り」
実は日本だけじゃなく世界の他の言語でも、事情は同じですです。何かに喩えることによってしか伝える方法がないなんて、不便を感じませんか?
「あのお酒、アニスっぽい香りがするんだよ!」
「アニスの香りがわからないんだけど」
香りを伝えようと思っている相手が、こちらが出す例えを何一つ感じたことがないとしたら、何を言っているかさっぱりわからず、伝えられません。
香りの表現が少ない理由
嗅覚に関する科学的な研究は、他の感覚より遅れてきました。歴史的に、嗅覚は五感の中で最も下層の感覚として扱われてきたからです。動物と違って、私達は真っ先に嗅覚で状況を判断するという場面は(腐っている、ガスが漏れている、などあるにしても)少ないですものね。
私たちは、意識が向かないようなことに呼び名をつけてこなかったのです。
言葉はそもそも、生きていくためにコミュニケーションをとったり例示するために発達してきました。他の感覚器より、嗅覚から情報をより細かく理解するために言語化する必要性は少ない、と人類は判断してきたのかもしれません。
ちなみにマレーシアの一部で話されているジャハイ語族やタイのジャングルに暮らすマニク語族には、香りを表現する言葉がたくさんあるそうです。
湿度が高く、香りに満ちたジャングルの中での暮らす人々には、鼻から得る情報をより細かく理解する必要性があったのだと考えられています。香りに囲まれた世界に住んでいると、その香りを具体化するために語彙を増やす必要が出てきます。
現代人にとっての香りの語彙力
さて、ジャングルでもなく命の危険にさらされないこの日本では、新しいコミュニケーションのためにそろそろ香りのボキャブラリーが増えても良いころです。オンラインで世界中の情報が時差なく入り、視覚情報が増えた現代。嗅覚の体験価値が高まる時代だと思うのです。
マドレーヌの香りを表現するピッタリの言葉がいつか生まれたらいいなぁと考えています。